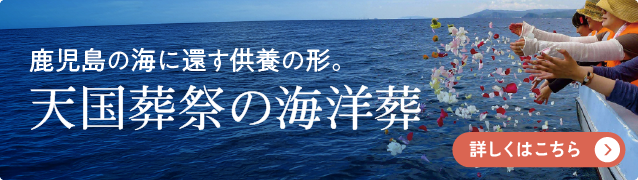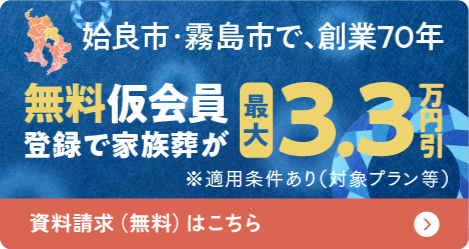こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の遠藤です。
一人暮らしをしている方の中には、「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけてしまわないか」「手続きがわからず、家族を困らせてしまうのでは」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、一人暮らしの方が亡くなった際に必要となる手続きの流れから、生前に備えておける対策までを詳しく解説します。
正しい知識を持つことで、ご自身の最期の準備ができ、ご家族の負担を軽減できます。
ぜひ最後までご覧ください。

一人暮らしの方が死亡した場合の対処手順とは?
一人暮らしの方が亡くなった場合、まず病院や警察から身元保証人やご家族へ連絡が入ります。
賃貸住宅にお住まいの場合は、大家さんや管理会社から連絡が入ることもあります。
以下は、死亡確認から葬儀、そして各種手続きまでの一般的な流れです。
- 医師から死亡診断書を受け取る
- 死亡届を7日以内に市区町村役場へ提出、火葬許可証が交付される
- 葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀・火葬を執り行う
- 年金や健康保険の資格喪失手続き
- 各種契約の解約と未払金の精算
- 遺品整理と住居の明け渡し
これらの手続きは基本的に相続人が行いますが、相続人がいない場合は自治体が対応するケースもあります。
一人暮らしの死亡後に行う手続き
一人暮らしの方が亡くなったあとに必要な手続きはさまざまあります。
主要な手続きを期限とともに詳しくご紹介します。
死亡届の提出と火葬許可証の交付
医師から死亡診断書を受け取ったあと、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。
死亡届は診断書や検案書と一体になっているケースも多いです。
死亡届は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地で手続きが可能です。
死亡届を提出すると同時に、火葬許可証が交付されます。
これがなければ火葬を行うことはできません。
提出義務は原則として親族にありますが、親族が対応できない場合は、大家さんや管理人が代行することもあります。
葬儀・火葬・埋葬の手配と実施
通常は死亡診断書を受け取ったあとに葬儀社と連絡を取り、葬儀の日程や内容を決めて葬儀場、火葬場の予約を行う手順となります。
身寄りがない方や親族と連絡が取れない状況では、自治体が火葬を担当する場合があります。
親族による遺骨の引き取りがないときは、自治体が無縁仏として埋葬を行います。
年金・健康保険の資格喪失手続き
年金を受給している場合は、年金の受給停止手続きが必要です。
いずれも以下の期限内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します。
- 厚生年金:死亡後10日以内
- 国民年金:死亡後14日以内
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合も、14日以内に「資格喪失届」の提出と保険証の返却が必要です。
各種契約の解約と未払金の精算
契約しているサービスなどを解約します。
例として、賃貸住宅、電気・ガス・水道などの公共料金、携帯電話、インターネット、クレジットカードなどが挙げられます。
法的な期限はありませんが、契約が続いている間は費用が発生し続けるため、早めの対応が必要です。
見落としがちな契約としては、百貨店の会員サービスやジム、定期購入(サブスク)などがあります。
通帳やクレジットカードの明細を確認し、定期的な引き落としの有無を把握しましょう。
医療費や家賃の未払い分も精算が必要です。
原則として相続人や連帯保証人以外には支払い義務は発生しませんが、トラブルを避けるために整理しておくことをおすすめします。
遺品整理と住まいの片付け
住んでいた部屋の片付けと遺品整理も重要な手続きです。
特に賃貸住宅の場合、早急に明け渡しを行う必要があります。
遺品の中に金銭的価値があるものが含まれる場合、それは相続財産と見なされ、相続人以外の方が勝手に処分することはできません。
相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、「相続財産清算人」の選任が必要です。
相続・税務関係の手続き
相続が発生する場合は、遺言書の有無を確認し、相続人全員で遺産分割について話し合うことになります。
収入がある場合は、相続人が相続開始を知った日から4カ月以内に準確定申告を行います。
相続税の対象となる場合は、10カ月以内に申告・納税手続きを完了させる必要があります。
不動産や預貯金についても、相続確定後に名義変更が必要なので、契約関係などの情報と一緒にまとめておきましょう。
一人暮らしでも死亡後の手続きを生前に準備できる

死後の手続きを円滑に進めてもらうためには、生前の備えが重要です。
事前の対策でご家族の負担を減らし、ご自身の希望も実現しやすくなります。
死後事務委任契約の活用
死後事務委任契約とは、死亡後の事務手続きを信頼できる第三者に委任する契約です。
委任内容には、死亡届の提出、葬儀の手配、公共料金の支払い、遺品整理などが含まれます。
親族や友人に依頼することも可能ですが、より確実な対応を希望する場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
なお、死後事務委任契約では財産の承継は行えないため、財産を指定する場合は遺言書の作成が別途必要です。
遺言書の作成
相続人がいる場合は法定相続が適用されますが、希望に沿った相続の実現や、相続人がいない場合には、遺言書が不可欠です。
遺言書を作成しておけば、相続人以外の方にも財産を遺すことができ、自身の意思を反映できます。
遺言書には複数の種類がありますが、
家庭裁判所の検認が不要で、内容の実現性が高く、手続きもスムーズなのは公正証書遺言です。
葬儀の事前相談
葬儀の事前相談とは、ご自身が亡くなる前に、葬儀社に葬儀の内容や費用、流れなどを相談しておくことです。
事前相談をしてある程度プランを決めておけば、自身の希望に沿った葬儀を執り行えることに加え、遺されたご家族の手間を減らすことにもつながります。
時間をかけて検討できるため、予算に合わせた葬儀プランを選択することも可能です。
このような準備を生前に行うことで、ご自身の希望する葬儀や供養を実現でき、ご家族の精神的・経済的負担も軽減できます。
身寄りがない方の場合は、死後の手続きを誰が行うかという問題も生前に解決でき、手続きの漏れや遅れも防げるでしょう。
さらに、金銭的な負担を事前に明確にできるため、予算に応じた準備が可能です。
終活についてより詳しく知りたい方は以下のコラムもぜひご参考ください。
一人暮らしの死亡後手続きは、生前準備で家族の負担を減らせる
一人暮らしの方が亡くなった際の手続きは多岐にわたりますが、生前に適切な準備をしておくことで、ご自身の意思を実現しながらご家族の負担も軽減できます。
死亡届の提出、葬儀、年金や保険の手続き、契約の解約、遺品整理など、やるべきことは多いですが、死後事務委任契約や遺言書、葬儀の事前相談などを活用して準備をしておくことができます。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。