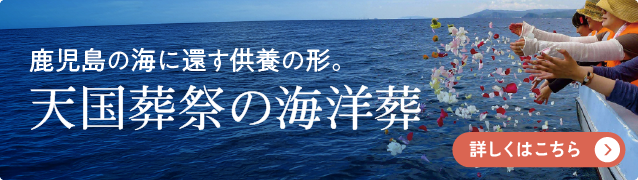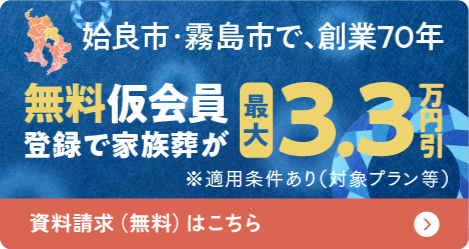こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。
大切な方との別れは突然訪れることが多く、「何をすれば良いのか」と不安に感じる方も少なくありません。
老人ホームで亡くなった場合、病院とは異なる対応が必要になることもあるため、事前にやるべきことを確認しておくと良いでしょう。
今回は、ご家族が入居されている老人ホームで亡くなられた場合に必要な手続きや注意点についてご説明します。
いざというときに慌てず対応できるよう、最後までお読みいただければ幸いです。

老人ホームで亡くなった場合の流れ
ご家族が老人ホームで亡くなられた場合、どのように対応すれば良いのか、流れを確認しておきましょう。
基本的な流れは以下のとおりです。
①危篤連絡を受ける
多くの場合、老人ホームのスタッフから容態の急変や危篤状態に関する連絡が入ります。
連絡を受けたら、できるだけ早く施設に向かいましょう。
②ご臨終・死亡宣告
息を引き取った後、施設の嘱託医または提携医療機関の医師による死亡確認が行われます。
病院とは異なり、常駐の医師がいない場合があるため、医師の到着に時間がかかることもあります。
また、死亡診断書はこの時点で発行されます。
役所への提出に必要なため、大切に保管してください。
③エンゼルケア
施設によっては、看護師や介護士によるエンゼルケアが行われます。
エンゼルケアとは、ご遺体の手当や衛生面の処置を行い、死化粧を施すなど、死後の姿をきれいに整える処置です。
エンゼルケアを行わない施設の場合は、葬儀会社に連絡した際にその旨を伝え、処置してもらうようにしましょう。
④葬儀会社へ連絡し、ご遺体の搬送・安置
老人ホームには安置室がない場合が多いため、ご遺体を搬送する必要があります。
搬送先は、自宅、葬儀社や斎場の安置室などです。
事前に搬送先を決めておくとスムーズです。
⑤葬儀の準備
ご遺体が安置された後、葬儀会社と打ち合わせを行い、葬儀の形式や日程を決めます。
家族葬、一般葬、直葬など、希望に合わせたプランを選択しましょう。
また、火葬場の手配や式場の予約、参列者の人数なども検討します。
⑥親族や関係者へ連絡
故人様の親族や親しい友人、関係者へ訃報を伝えます。
葬儀の場所や日程がわかっている場合は、このときあわせてお伝えしましょう。
⑦葬儀
準備が整ったら、葬儀を執り行います。
僧侶の手配や香典の受け取りについても事前に決めておくと、当日の進行がスムーズです。
葬儀後は、香典返しの手配や、初七日法要や四十九日法要の準備などを行います。
くわしくは、「喪主がやることを通夜から葬儀後までわかりやすく解説」をご覧ください。
老人ホームで亡くなった場合の注意点

老人ホームでご家族が亡くなられた場合、病院とは異なる点がいくつかあります。
事前に確認しておきましょう。
他の入居者への配慮
老人ホームは複数の方が生活する場所です。
ご遺体の搬送時には、他の入居者の方々へ配慮しましょう。
施設のスタッフと協力し、静かに、そして可能な限り他の入居者の目に触れないようにすることが望ましいです。
安置場所の確保
老人ホームでは、スペースが限られており、亡くなられた後はすみやかに搬送の手配が必要になることが多いです。
そのため、葬儀社に依頼し、ご遺体を自宅や安置施設へ搬送するのが一般的です。
葬儀社が決まっていない場合は、施設から紹介してもらえることもあります。
搬送にかかる費用
遺体搬送にかかる費用は、通常、移動距離などによって変わります。
老人ホームと安置場所が遠い場合、搬送費用が高額になる可能性があるため、注意しましょう。
また、夜間や早朝の搬送では追加料金、有料道路や高速道路を利用する場合は、その料金が必要となることがあります。
葬儀プランによっては一定距離までの搬送費用が含まれていることもあるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
施設内での葬儀
一部の老人ホームでは、施設内で葬儀を行える場合があります。
小規模なお別れの会を開くことができる施設もあり、入居者やスタッフが参列しやすいというメリットがあります。
ただし、施設によって方針が異なり、宗教儀式を伴う葬儀が制限されることもあるため、事前に施設の対応を確認しておくことをおすすめします。
老人ホームで亡くなった後の手続きと注意点
老人ホームでご家族が亡くなられた後は、一般的な死亡時の手続きに加え、施設特有の手続きも必要になります。
悲しみの中でさまざまな手続きを進めるのは大変ですが、事前に流れを把握しておくことで、落ち着いて対応することができます。
ここでは、一般的な手続きと老人ホーム特有の手続きを分けてご紹介します。
一般的な手続き
まずは、病院やご自宅で亡くなられた場合も、老人ホームで亡くなられた場合も行う、一般的に必要な手続きの主なものを確認しましょう。
死亡届の提出
死亡診断書を受け取った後、7日以内に市区町村役場に提出します。
年金の停止手続き
年金事務所や市区町村の窓口で手続きします。
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に届け出が必要です。
健康保険・介護保険の資格喪失手続き
市区町村の窓口で手続きします。
保険証の返却が必要な場合が多く、届け出期限は14日以内が一般的です。
各種保険金の請求手続き
生命保険や医療保険に加入していた場合は、保険会社に連絡します。
老人ホーム特有の手続き
以下が老人ホームで亡くなられたとき特有の主な手続きです。
退去手続き
施設との契約に基づき、退去の手続きを行います。
利用料の精算
日割り計算された最終月の利用料や、追加サービス料の精算を行います。
保証金の返還手続き
入居時に保証金を支払っていた場合は、返還手続きを行います。
施設によって退去期限や手続きの詳細は異なりますので、早めに確認しておくことをおすすめします。
施設スタッフへのお礼
手続きではありませんが、葬儀が終わり落ち着いたら、老人ホームを訪問し、生前お世話になった感謝の気持ちを伝えましょう。
施設のスタッフが葬儀に参列してくれた場合は、お礼の言葉も忘れずに伝えてください。
遺品整理や相続に関する注意点
遺品整理を始める前に、まずは遺言の有無を確認しましょう。
遺言が残されている場合、故人様の意思を尊重し、指示に従って整理を進める必要があります。
老人ホームでの遺品整理は、物が比較的少ないことが多いですが、他の入居者への配慮として、作業は静かに行うことが望ましいです。
老人ホームでの退去作業は速やかに行う必要があるため、ホーム内で遺品の処分はせず、家に持ち帰ってから、遺言に基づいて要・不要の判断をします。
また、故人の財産に関する相続手続きは法律に基づいて行われます。
預貯金、不動産、生命保険など、財産の種類を把握し、必要な手続きを進めましょう。
相続には期限があり、相続放棄や限定承認は3カ月以内、相続税の申告・納付は10カ月以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、すべての財産や負債を相続することになるため、早めに確認し、専門家に相談することをおすすめします。
老人ホームで亡くなった場合の手続きを知り、落ち着いた対応を
老人ホームで大切な方が亡くなられた場合、病院とは異なる対応や手続きが必要となります。
特に老人ホームではご遺体の安置スペースが限られることから、速やかに搬送するケースが多いです。
施設スタッフと連携しながら、対応を進めることが重要です。
老人ホームでは、他の入居者への配慮を忘れないようにしましょう。
また、一般的な死亡後の手続き以外にも、退去手続きや利用料の精算など、老人ホーム特有の手続きも必要です。
家族が老人ホームで亡くなった際の注意点を事前に確認しておくと、万一の際も慌てずに対処ができるでしょう。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は「天国葬祭」にぜひご相談ください。