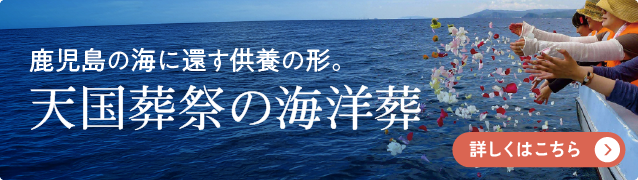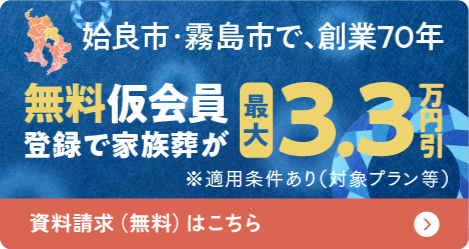こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の徳田です。
ご家族が自宅で亡くなった場合、動揺して何をすべきかわからなくなってしまうのは当然のことです。
病院での看取りとは異なり、自宅での対応には自宅だからこその手順や注意点があります。
今回のコラムでは、自宅で亡くなった場合に最初にすべきことから葬儀社への連絡、その後の手続きまで、一連の流れを詳しく解説します。
いざというときに落ち着いて対応できるよう、参考にしていただければ幸いです。

自宅で亡くなった場合に最初にすること
ご家族が自宅で亡くなった場合、まず行うべきは、死亡の確認と関係機関への通報です。
かかりつけ医がいるかどうかで対応が異なります。
かかりつけ医がいる場合
定期的に診療を受けていたかかりつけ医がいれば、まずはその医師または医療機関に連絡しましょう。
故人様が24時間以内に診察を受けており、持病による自然死であれば、医師が臨終に立ち会っていなくても死亡診断書を発行してもらえます。
診療から24時間以上経過している場合でも、医師が訪問して死亡の状況を確認できれば、診断書が発行されます。
かかりつけ医がいない場合
かかりつけ医がいない場合や、生死の判断がつかない状況のときは救急車を呼んでください。
ただし、救急車は基本的に救命を目的としており、すでに死亡していると判断された場合は搬送できません。
この場合、救急隊がそのまま警察に引き継いでくれます。
警察による検視の流れ
警察へ通報すると、事件性の有無を確認するために以下の手順で検視が行われます。
- ご遺族への聴取
- 実況見分
- 警察官または検視官による検視
事件性が否定されれば、「死体検案書」が交付されます。
この書類は、死亡診断書と同等の効力を持ち、各種手続きに使用されます。
死因が明確でない場合は、さらに詳しい検案や解剖が必要になることもあります。
医師や警察が到着するまでの間は、ご遺体を動かさず、現場の状況をそのまま保ちます。
入浴中などのケースでも、着替えをさせるなどの行為は控えましょう。
また、エアコンや扇風機を使用して室温をできるだけ低く保つことも心がけてください。
自宅で亡くなった場合の葬儀社への連絡と搬送の流れ
死亡診断書または死体検案書を受け取ったあとは、速やかに葬儀社に連絡し、遺体の搬送や葬儀の手配をします。
あらかじめ葬儀社を決めていない場合は、複数社に連絡した上で費用や対応を聞いて決めても良いでしょう。
一般的には、ここでご遺体の搬送をお願いした葬儀会社に、葬儀まで依頼します。
葬儀社への電話連絡時には、以下の内容を整理して伝えるとスムーズです。
- 故人様の状態(死亡確認済みであること)
- ご遺体の搬送希望の有無
- 希望する葬儀の内容や予算
安置場所の選択
ご遺体の安置先は、自宅か葬儀会社の安置場所のどちらかを選択することになります。
自宅に安置するのは、家族と最期の時間を落ち着いて過ごせるメリットがあります。
ただし、温度管理や安置場所の確保などが必要です
葬儀社の安置施設に搬送する場合は、適切な環境でのご遺体管理を任せることができ、自宅にスペースがない場合にも対応可能です。
搬送の手配
ご遺体を搬送する場合は、葬儀社が決まり次第、専用の車両とスタッフによる遺体搬送が行われます。
搬送には、死亡診断書または死体検案書の提示が必要ですので、あらかじめ手元に準備しておきましょう。
亡くなった後には「エンゼルケア」と呼ばれる遺体の清拭・整容が行われます。
詳しくはこちらのコラムもご覧ください。
自宅で亡くなった場合の死亡届や火葬の手続き

死亡が確認されたあとは、定められた期限内に必要な法的手続きを進めていきます。
死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書または死体検案書を受け取ってから7日以内に提出します。
期限を過ぎた場合、戸籍法に基づき3万円以下の過料が科せられる可能性があります。
提出先は、故人様の死亡地、本籍地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
届出人は、親族・同居人のほか、葬儀社などの代理人でもかまいません。
提出時には死亡診断書または死体検案書の原本が必要となるため、紛失しないように保管してください。
火葬許可証の申請
火葬を行うには、「火葬許可証」が必要で、この手続きも死亡から7日以内に行う必要があります。
自治体によっては「埋火葬許可申請書」など、書式や名称が異なる場合もあります。
一般的には、死亡届の提出と同時に申請します。
申請後、火葬許可証が交付され、火葬場の使用が可能となります。
火葬後、許可証に火葬場の証明印が押され「埋葬許可証」となります。
埋葬許可証は納骨時に必要です。
親族への連絡
手続きがひと通り終わったら、親族への訃報連絡も忘れず行いましょう。
まずは近親者から順に連絡をし、遠方の親族へは葬儀の日程が決まった段階で知らせると良いでしょう。
なお、死亡診断書の発行には数千~数万円程度、死体検案書の発行には3~10万円程度の費用がかかることが一般的ですが、状況や地域によっても異なることがあります。
自宅で亡くなった場合の手順を把握し落ち着いた対応を
家族が自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医がいるならかかりつけ医に、そうでない場合にはまずは救急車を呼び、死亡確認と死亡診断書または死体検案書の発行を受けます。
医師や警察が到着するまではご遺体を動かさず、室温は低く保ちましょう。
その後は速やかに葬儀会社へ連絡し、搬送や安置、7日以内に死亡届と火葬許可証の申請を行います。
手順をあらかじめ把握しておくことで、突然の別れに動揺せず手続きを進め、穏やかなお見送りができるでしょう。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。