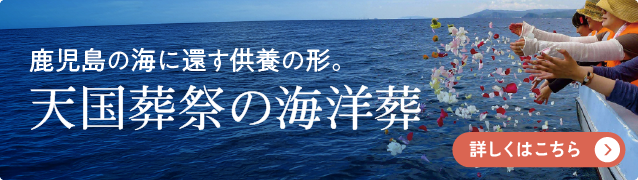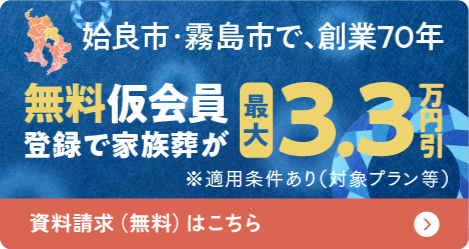こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の徳田です。
突然の訃報を受けた際「忌引き休暇は何日取れるのか」「どのように申請すれば良いのか」と迷われる方は多いでしょう。
身近な方を失った悲しみの中で、職場への連絡や手続きを行うのは心身ともに負担が大きいものです。
今回は、忌引き休暇の取得日数や連絡の方法、復帰時のマナーまで詳しく解説いたします。
いざというときに慌てることなく対応ができるよう、準備しておきましょう。

目次
忌引き休暇は何日が一般的?
忌引き休暇の日数は、故人様との関係性や企業の規定によって異なります。
まずは忌引き休暇の基本的な仕組みと、一般的な取得日数について確認していきましょう。
忌引き休暇の基本的な仕組み
忌引き休暇とは、家族や親族が亡くなった際に、葬儀への参列や諸手続きのために取得できる休暇制度です。
「喪に服す」という意味を持つ忌引きは、故人様への弔意を表し、心の整理をするための大切な期間でもあります。
ただし、忌引き休暇は労働基準法で定められた法定休暇ではありません。
各企業が福利厚生の一環として独自に設けている制度のため、取得条件や日数は会社によって異なります。
そのため、ご自身の勤務先の就業規則を事前に確認しておくことが重要です。
対象となる親族の範囲(親等別)
一般的に忌引き休暇の対象となるのは、3親等以内の親族です。
企業によっては2親等までを対象とする場合もあるため、詳細は就業規則で確認すると良いでしょう。
| 親等 | 親族の範囲 |
| 0親等 | 配偶者 |
| 1親等 | 父母、義父母(配偶者の父母)
子ども |
| 2親等 | 祖父母、義祖父母(配偶者の祖父母)
兄弟姉妹、義兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹) 孫 |
| 3親等 | 曾祖父母
おじ・おば(叔父・叔母) 甥・姪 |
なお、親等とは血縁関係の近さを表す単位で、数字が小さいほど関係が近いことを示します。
親族別の一般的な取得日数
忌引き休暇の日数は、故人様との関係の深さに応じて設定されています。
以下が一般的な目安となる日数です。
配偶者:7~10日
最も身近な存在である配偶者の場合、喪主を務める可能性が高く、葬儀の準備から事後手続きまで多くの対応が必要となります。
そのため、忌引き休暇の日数も長めに設定されていることが多いです。
喪主の具体的な役割については「喪主がやることを通夜から葬儀後までわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
あわせて参考にしてくださいね。
父母・子:3~7日
実の父母の場合は5~7日、義父母の場合は3~5日程度が一般的です。
子どもの場合も5~7日程度の休暇が認められることが多いでしょう。
祖父母・兄弟姉妹:1~3日
実の祖父母や兄弟姉妹の場合は3日程度、配偶者の祖父母や兄弟姉妹の場合は1日程度となるのがほとんどです。
その他(おじ・おばなど):0~1日
3親等のおじ・おばや甥・姪の場合、1日程度または対象外とする企業もあります。
土日を挟んだ場合の取り扱い
忌引き休暇期間中に土日や祝日が含まれる場合の扱いは、企業によって異なります。
「土日を含む」と記載がある場合
金曜日から3日間の忌引き休暇を取得すると、金・土・日が休暇扱いとなり、月曜日から出勤となります。
「土日を除く」という記載がある場合
同じく金曜日から3日間の忌引き休暇でも、土日を除いて金・月・火が休暇となり、水曜日から出勤となります。
公務員と民間企業の違い
公務員の場合、忌引き休暇は人事院規則や各自治体の条例で明確に定められています。
国家公務員の場合、配偶者・父母は7日、子は5日、兄弟姉妹・祖父母は3日などとなっています。
また、公務員の忌引き休暇は基本的に有給扱いとなるのも特徴です。
忌引き休暇を取得する際の伝え方

忌引き休暇の申請は急を要する場合が多いため、連絡方法と伝え方を知っておくことが大切です。
ここでは、申請のタイミングから具体的な連絡方法まで詳しくご説明します。
申請のタイミングと連絡方法
忌引き休暇は、一般的には亡くなった当日、または翌日から取得することになります。
そのため、連絡は亡くなったことを知った時点で可能な限り早急に行いましょう。
忌引き休暇の連絡は、基本的に直属の上司に対して行います。
出社可能な場合は対面で報告をし、難しい場合は電話で連絡をしましょう。
深夜や早朝に知った場合は一度メールで連絡し、就業時間になった時点で改めて電話で詳細を伝えるのが良いでしょう。
伝えるべき内容
忌引き休暇の申請時には、以下の内容を明確に伝える必要があります。
- 亡くなった方との続柄
- 死亡した日時
- 希望する休暇期間
- 葬儀の日程と場所(分かる範囲で)
- 休暇中の緊急連絡先
上司が葬儀に参列される可能性もあるため、通夜・告別式の日程や会場についても併せて伝えておくと安心です。
忌引き休暇を取得する際に注意したいこと

ここでは、休暇取得時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
就業規則の確認を必ず行う
大切なのは、勤務先の就業規則を確認することです。
忌引き休暇は法定休暇ではないため、企業によって制度の内容が異なります。
確認すべき項目は以下のとおりです。
- 忌引き休暇制度の有無
- 対象となる親族の範囲
- 親族別の取得可能日数
- 休暇の起算日
- 土日祝日の扱い方
就業規則は入社時に配布されるほか、社内の共有ファイルや社員向けのホームページなどで確認できる場合が多いでしょう。
わからない場合は、人事担当者に問い合わせることをおすすめします。
休暇中の給与の有無について確認
忌引き休暇中の給与の取り扱いも、企業によって異なります。
一般的には以下のパターンがあります。
- 有給扱い:通常の給与が支払われる
- 無給扱い:給与は支払われない
- 有給休暇消化:年次有給休暇を使用する
多くの企業では有給扱いとしていますが、パートやアルバイトの場合は無給となることもあります。
必要な証明書類の準備
企業によっては、忌引き休暇の取得に際して証明書類の提出を求められる場合があります。
一般的に必要となる書類は次のようなものです。
- 会葬礼状
- 葬儀施行証明書
- 死亡診断書のコピー
- 火葬許可証のコピー
- 葬儀の案内はがき
これらの書類は葬儀後に入手できるものが多いため、休暇明けに提出することになります。
必要な書類は事前に確認し、必要があれば葬儀社にも協力を依頼しておくと良いでしょう。
遠方での葬儀の場合の対応
葬儀が行われる場所が遠方で移動に時間がかかる場合、定められた休暇日数では足りない可能性もあります。
移動時間は一般的に忌引き休暇に含まれません。
移動日を含めた休暇期間を相談する、有給休暇と組み合わせるなどの対応も検討しましょう。
忌引き休暇を取得したあとにすべきこと

忌引き休暇から職場に復帰する際は、休暇中にサポートしてくれた方への配慮を忘れずに、円滑な業務復帰を心がけましょう。
休暇明けの挨拶とお礼
職場復帰の際は、まず直属の上司に休暇明けの報告を行います。
「おかげさまで、無事に葬儀を終えることができました」といった簡潔な報告と、休暇取得の感謝を伝えましょう。
続いて、業務をフォローしてくれた同僚や部下にも個別にお礼の挨拶をします。
急な休暇で迷惑をかけたことへのお詫びや、代理対応してくれたことへの感謝を丁寧に伝えることが大切です。
香典返しの準備
職場の方から香典をいただいた場合は、香典返しを準備する必要があります。
いただいた香典の3分の1から半額程度の品物をお返しするのが一般的です。
なお、香典返しには次のような品物が多く選ばれています。
- お茶やコーヒーなどの嗜好品
- タオルや石けんなどの日用品
- お菓子やのりなどの食品
香典返しには、感謝の気持ちを込めた挨拶状を添えることが一般的です。
葬儀が無事に終了したことの報告と、お心遣いへの感謝を記載しましょう。
必要書類の提出
就業規則で証明書類の提出が義務付けられている場合は、休暇明けに速やかに提出します。
会葬礼状や死亡診断書のコピーなど、必要な書類を人事担当者に提出しましょう。
書類に不備がある場合は再提出が必要になることもあるため、事前に内容を確認しておくことをおすすめします。
忌引き休暇が何日取れるかは会社で異なる。必要な書類も確認を
忌引き休暇は、故人様との関係性によって3日から10日程度の取得が可能ですが、具体的な日数は企業の就業規則によって異なります。
申請時は直属の上司に速やかに連絡し、故人様との続柄や希望する休暇期間を明確に伝えることが重要です。
また、忌引き休暇の申請には証明書類が必要なこともあります。
休暇中の給与の有無についても念のため確認しておきましょう。
復帰時は関係者への挨拶をし、お礼や香典返しなどの配慮を忘れずに対応することも大切です。
天国葬祭では「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。