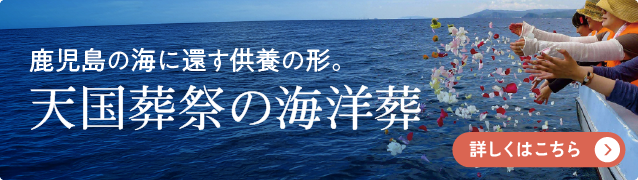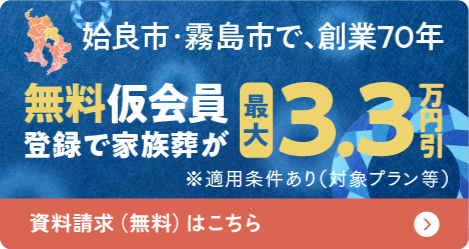こんにちは。 姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。
大切な方を亡くされたとき、葬儀の準備を進める中で「納棺」という儀式について初めて知る方も多いのではないでしょうか。
納棺は故人様があの世への旅立ちに向けた支度を整える重要な儀式であり、同時にご遺族が故人様と最後にゆっくりとお別れできる貴重な時間でもあります。
今回は、納棺とはどのような儀式なのかや、具体的な流れや費用、注意点などについて詳しくご紹介します。

葬儀での「納棺」とは?
納棺とは、故人様のご遺体を清めてあの世への旅立ちに向けた支度を行い、副葬品と呼ばれる思い出の品などとともにお棺にお納めする儀式のことです。
納棺の意味と目的
納棺には大きく2つの意味があります。
一つ目は、故人様があの世へ安らかに旅立てるよう、この世での汚れや疲れを取り除き、旅の準備を整えることです。
故人様が安らかに次の世界へ向かえるよう、旅立ちの身支度を整えます。
二つ目は、ご遺族にとって故人様との別れを受け入れ、心の整理をつける大切な時間という意味です。
故人様のお世話をする最後の機会であり、家族だけでゆっくりと故人様を囲んでお別れができる貴重なひとときとなります。
納棺を行うタイミング
納棺を行うタイミングは地域によって異なりますが、一般的には通夜が始まる3~5時間前に行われることが多いです。
例えば、通夜の開式時刻が18時~19時頃の場合、納棺の儀式は13時~16時頃に執り行われます。
納棺にかかる時間は内容によって異なりますが、30分~2時間程度が目安となります。
納棺師について
納棺は葬儀社のスタッフや納棺師によって行われることがほとんどです。
納棺師は映画「おくりびと」で一躍有名になった職業で、故人様を棺に収めるための処置を専門的に行います。
故人様のお体をきれいにして着替えや身づくろいを行い、生前のような安らかな表情を作るための施術なども行います。
納棺の儀式の流れ
納棺の儀式を滞りなく進めるためには、具体的な流れと副葬品の扱いについて理解しておくことが大切です。
ここでは、納棺儀式の詳しい手順と、棺に入れて良いものと避けるべきものについて詳しくご説明します。
納棺の儀式の具体的な手順
納棺における一つひとつの工程には深い意味が込められており、故人様の安らかな旅立ちを願う大切な儀式です。
末期の水をとる
末期の水とは、故人様の口元を水で湿らせる儀式で、「死に水を取る」とも呼ばれます。
お釈迦様が入滅の際に水を求めたことに由来するとされ、故人様があの世で渇きに苦しまないようにとの願いが込められています。
具体的には、割り箸の先に脱脂綿を巻いて白い糸で固定し、お椀の水に浸して故人様の唇を湿らせます。
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹の順番で、故人様との関係が深い方から行うのが一般的です。
脱脂綿を上唇の左側から右側へ、下唇の左側から右側へとなぞるように動かし、唇を潤す程度に留めます。
湯灌(ゆかん)で身体を清める
湯灌(ゆかん)とは、故人様のお体をお湯で洗い清める儀式です。
この世での疲れや汚れを洗い落とすという意味を持ち、故人様があの世へ清らかな状態で旅立てるよう願いを込めて行われます。
現在では専用の設備を使用して、湯灌師や葬儀社のスタッフが行うことが一般的です。
移動可能な湯灌用の浴槽を用いて、故人様のお体を丁寧に髪の毛から足先まで洗い清めます。
ひげを剃ったり爪を切ったりすることもでき、プライバシーに配慮して大きなタオルで覆いながら行われます。
設備がない場合や費用を抑えたい場合は、お体を拭いて清める「清拭」のみ行うこともあります。
この場合は親族がタオルで故人様のお体を拭き清める方法もあります。
死化粧を施す
死化粧とは、故人様が元気だった頃の表情に近づけるよう化粧を施すことです。
具体的には、顔そりなどの手入れをして髪の毛を整え、ファンデーションやコンシーラー、チーク、口紅などを使ってメイクを施します。
ご遺体は乾燥しやすいため、保湿も重要な処置の一つです。
やつれが目立つ場合には頬に綿を含ませて顔の輪郭を整えることもあります。
故人様が生前に愛用していた化粧品を使用することも可能で、ご家族の手でお化粧を施すこともできます。
死装束(しにしょうぞく)を着せる
死装束(しにしょうぞく)とは、亡くなった方が最後に身につける衣装のことです。
仏式では一般的に白の着物タイプの衣装である「経帷子(きょうかたびら)」を着せ、笠や脚絆(きゃはん)、手甲(てっこう、てこう)、頭陀袋(ずだぶくろ)などの小道具をつけて旅支度を整えます。
頭陀袋には三途の川の渡し賃である「六文銭(ろくもんせん)」を入れますが、現在では実際のお金ではなく紙に印刷されたものが使用されます。
これらの装身具は、故人様があの世への旅路を無事に歩めるよう、僧侶や巡礼者の姿に準えたものです。
近年では死装束も多様化しており、故人様が生前に愛用していた洋服を着せることも可能です。
宗教上の問題がなく、ご家族の理解が得られる場合は、故人様らしい装いでお見送りすることができます。
副葬品として入れて良いもの・ダメなもの
納棺の際には、故人様の愛用品や思い出の品を「副葬品」として一緒にお棺に納めることができます。
副葬品は故人様があの世でも安らかに過ごせるよう、また生前の思い出を大切にしたいというご遺族の気持ちから納められます。
【入れて良いもの】
- 花(故人様が好きだった花や育てていた花)
- 手紙(ご遺族から故人様への手紙や大切にしていた手紙)
- 写真(故人様が写っている写真や趣味の写真)
- お菓子(缶や瓶から取り出したもの)
- 故人様のお気に入りの洋服(金属製の装飾は外す)
- 趣味に関するもの(燃えやすいものに限る)
【入れてはいけないもの】
- 金属製品(眼鏡、腕時計、指輪、アクセサリー、入れ歯など)
- ガラス製品
- プラスチック製品(ペットボトル、ビニール、発泡スチロールなど)
- 爆発の危険があるもの(ライター、スプレー缶、缶飲料、乾電池など)
- 水分の多いもの(果物類など)
- 革製品やゴム製品
- 分厚い本やCD・DVD
- お金(硬貨、紙幣)
これらは火葬の際に不完全燃焼を引き起こしたり、有毒ガスを発生させたり、火葬炉を損傷させる可能性があるため避ける必要があります。
このほか、生きている人が写っている写真も、「一緒に連れて行かれてしまう」という考えから、入れないほうが良いとされています。
副葬品については下記コラムで詳しくご紹介していますので、こちらもご覧ください。
納棺の儀式にかかる費用は?

納棺の儀式にかかる費用は、どのような内容を希望するかによって異なります。
基本的な納棺作業は葬儀プランに含まれていることが多いですが、湯灌や死化粧などはオプション料金が発生する場合があります。
費用の目安と内訳
納棺に関する費用は葬儀社によって設定が異なりますが、一般的な目安をご紹介します。
湯灌の費用
湯灌を希望する場合、葬儀社によって異なりますが、5万円から15万円ほどの費用がかかります。
シャワー式やバスタブの有無によって料金が変動します。
死化粧の費用
死化粧についても、基本的には別途料金がかかることが多いです。
簡単な身だしなみから本格的なメイクまで、内容に応じて費用が設定されています。
死装束の費用
死装束には柄が入ったものや高級な素材でできたものなどもあり、数千円のものから数万円まで幅広いため、葬儀社やご家族と相談し、ご予算に合わせて選択できます。
費用を抑える方法
納棺にかかる費用を抑えたい場合は、以下の方法があります。
- 湯灌は行わず清拭のみにする
- 故人様の愛用していたメイク道具を使ってご遺族がお化粧を施す
- 宗教上の問題がなく周囲の理解を得られるのであれば、死装束は購入せず、故人様のお気に入りの洋服を着せる
ただし、費用を抑える場合でも、故人様の尊厳を保ち、ご遺族が納得できる形でお見送りすることが重要です。
納棺の儀式でのマナーや注意点

納棺の儀式の際には、参列者や服装、マナーなどについていくつかの注意点があります。
事前に確認しておくことで、スムーズで心のこもった儀式を行うことができます。
立ち会える人の範囲
納棺の儀式に立ち会うのは、原則として故人様の近親者のみです。
配偶者、子ども、孫といった近親者が中心となり、友人や仕事関係者は基本的に立ち会いません。
これは納棺が故人様とご遺族のお別れの儀式であり、故人様に直接触れながら最後のお世話をする大切な時間だからです。
近親者以外は通夜や告別式に参列することで、故人様にお別れを告げることになります。
ただし、故人様が生前に「親しい友人にも立ち会ってもらいたい」と希望されていた場合など、特別な事情がある場合は柔軟に対応することも可能です。
立ち会う際の服装マナー
納棺の儀式に参加する際の服装は、実施場所によって異なります。
自宅で行う場合
近親者のみで執り行うこともあり、平服でも構いません。
平服とは略礼装のことで、男性の場合はスーツ、女性の場合はワンピースやダークカラーのスーツが基本です。
普段着でも良いと言われた場合は、スーツでなくてもかまいません。
ただし、ジーンズなどカジュアルな装いや、肌の露出が多いもの、色柄物の洋服は避けましょう。
斎場で行う場合
そのままお通夜に臨めるよう、あらかじめ喪服を着用して納棺の儀式に参加するのが一般的です。
男性の場合はスーツ・ネクタイ・靴下・靴をすべて黒に揃え、女性の場合も黒に統一しましょう。
服装については、こちらのコラムもご覧ください。
葬式の服装の種類やふさわしい服装とは?身だしなみ・マナーもご紹介
納棺を行う際の注意点
納棺の儀式をスムーズに進めるために、時間の管理や心構え、宗教的な違いについても把握しておきましょう。
時間について
納棺の儀式は故人様とのお別れの大切な時間のため、時間に余裕を持って参加しましょう。
遅刻しないよう、事前に葬儀社と時間を確認しておくことが重要です。
心構えについて
納棺は故人様の死を改めて実感する場面でもあります。
ご遺族であっても、気持ちの整理がつかない、ご遺体を見るのが辛いという方は、無理をして納棺に立ち会う必要はありません。
宗教・宗派による違い
仏教以外の宗教では納棺の方法が異なる場合があります。
神式では神衣を着せ、キリスト教では十字架やロザリオを納めるなど、それぞれの宗教に応じた作法があります。
葬儀の納棺は故人様との最後の大切な時間
納棺は故人様をお棺にお納めする大切な儀式であり、あの世への旅立ちに向けた準備を整える重要な意味を持っています。
末期の水、湯灌、死化粧、死装束の着用、副葬品の納棺という一連の流れを通じて、故人様の安らかな旅路を願うとともに、ご遺族にとっては最後のお別れの時間となります。
費用については湯灌を含めた場合に追加料金が発生することが多く、内容を調整することで費用を抑えることも可能です。
立ち会うのは近親者のみで、服装は実施場所に応じて平服または喪服を着用します。
副葬品については燃えるもののみ納めることができ、金属製品や水分の多いものは避ける必要があります。
事前に注意点も確認し、故人様らしい心のこもった納棺の儀式を執り行いましょう。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。