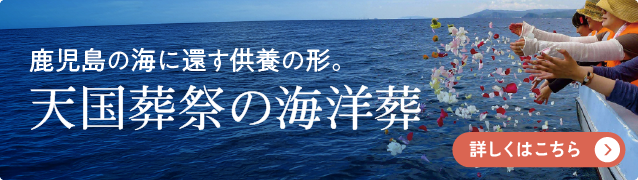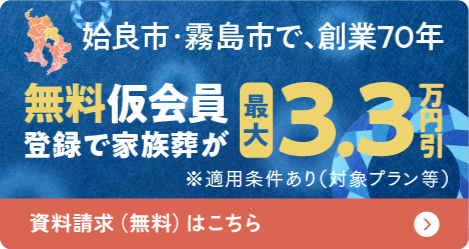こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。
葬儀に参列する際、受付で記入を求められる芳名帳に「どう書けば良いのだろう」と戸惑った経験はありませんか?
芳名帳は参列者の情報を記録・管理する大切な帳面で、正しい書き方やマナーを押さえておくことで、落ち着いて記入できます。
今回は、芳名帳の基本から書き方のルール、記入時のマナーまで詳しくご紹介します。
初めて参列する方や、会社の関係者として出席される方も、ぜひ参考にしてください。

芳名帳とは?芳名録・香典帳との違いも
芳名帳(ほうめいちょう)とは、葬儀に参列された方の名前と住所を記録・管理するための帳面です。
「芳名」は相手の名前を表現する尊敬語で、参列者への敬意を込めて芳名帳と呼ばれています。
地域によっては「芳名録」と呼ぶこともあります。
芳名帳・芳名録は、誰が葬儀に来てくださったのかを記録するとともに、香典返しやお礼状の送付先を把握するために使用されます。
特に多くの方が訪れる一般葬では、芳名帳がなければ誰が参列したのかを正確に把握できないため、受付に必ず設置されます。
芳名帳への記入は、受付で香典をお渡しするときに行います。
まず受付でご挨拶をしてから芳名帳に記入し、その後、香典をお渡しするという流れが一般的です。
参列者が多い場合は少し待ち時間が発生することもありますが、落ち着いて順番を待ちましょう。
香典帳との違い
葬儀の際に作成される帳面には、「香典帳」というものもあります。
香典帳は、葬儀や通夜で、誰にいくら香典をいただいたかを管理するための記録帳です。
香典帳は、葬儀後に芳名帳の情報を元にして喪主や遺族が作成するのが一般的です。
ただし、地域によっては参列者に芳名帳とあわせて香典帳への記入をお願いするケースもあります。
香典帳の作成方法については「香典帳の書き方ガイド。記入方法とポイントをわかりやすく」でも詳しくご紹介していますのであわせてご覧ください。
芳名帳の書き方の基本ルール
芳名帳には、基本的に参列者の名前と住所を記載します。
ただし、芳名帳の形式やどのような立場で参列するかによっても記載方法が少し異なることがあります。
違いを知っておくと、慌てずスムーズに記載できますので、ぜひ確認しておきましょう。
芳名帳の形式による違い
芳名帳は主にノート型とカード型の2種類があります。
それぞれの特徴と基本の書き方をご紹介します。
ノート型芳名帳
昔から使われている縦書きのノート形式です。
一般的には右から左へと記入欄が並んでおり、一行を使って住所を上に、名前を下に縦書きで記載します。
縦書きの場合、番地などの数字は漢数字で表記し、「0」は「〇」と記載します。
キリスト教式の葬儀では、横書きの芳名帳が使用されることもあります。
横書きの場合は左から右に記入し、数字はアラビア数字で記載しても構いません。
カード型芳名帳
カード型芳名帳は、最近増えている形式です。
1人1枚のカードに記入する形式で、参列者が多い場合でも記入の待ち時間を短縮できます。
カードには「ご芳名」と印字されている場合が多く、この場合は「ご芳」の部分を二重線で消してから記入します。
名刺を挿入できる仕様のものもあり、会社関係者として参列する場合は名刺を挿入するだけで済む場合もあります。
参列する立場ごとの違い
個人、夫婦、会社関係など、参列する立場ごとの記載すべき内容をご紹介します。
個人で参列する場合
個人で参列される場合は、基本の記載内容として自身の氏名と住所を正確に、読みやすい楷書で記載します。
後日、返礼品が送られる場合もあるため、郵便番号から番地、建物名、部屋番号まで省略せずに記載してください。
夫婦や家族で参列する場合
夫婦や家族で参列した場合も、それぞれの名前を書くのが基本です。
ノート型の場合は1行ずつ使って並べて書き、カード型の場合はそれぞれ1人1枚ずつ書きましょう
住所が同じであれば、「〃」を使って簡略化しても問題ありません。
地域の慣習によっては、夫の名前に「内」と記入して夫婦での参列を示すこともあります。
家族で参列した場合も、代表者の氏名に「家」と添えて記載する方法があります。
会社関係で参列する場合
仕事の関係で参列される場合は、会社の正式名称と所在地、部署名を記入した後に、自身の名前と住所を記載します。
会社を代表して参列される場合は、会社情報の後に「代表」と記入してから名前を書くとわかりやすいでしょう。
上司の代理として参列される場合は、上司の名前と会社情報を記入し、その左側に「代理」と記入した後に続けて自身の氏名を記載しましょう。
芳名帳を書くときのマナー

芳名帳の記入では、参列者側と受付側で気を付けたいマナーがあります。
適切なマナーを心がけることで、スムーズな葬儀進行と芳名帳の正しい活用につながります。
参列者のマナー
受付では、まず「この度はご愁傷様です」などの一言をお伝えして香典をお渡しし、その後、促されたタイミングで芳名帳の記入に進みます。
芳名帳の記載内容は長期間使う情報になるため、読みやすさと正確さを意識して記入します。
特に住所は返礼品の送付や法要の案内などにも使われるため、略さず丁寧に書きましょう。
郵便番号も書いておくと親切です。
ご遺族・受付側のマナー
受付では、芳名帳を開いて準備し、筆記具も十分に用意しておきましょう。
参列者がスムーズに記入できるよう、「恐れ入りますが、こちらにお名前とご住所の記入をお願いいたします」と声をかけます。
同時に受付で香典を受け取る場合は、「お預かりいたします」と一言添え、両手で丁寧に受け取ります。
声かけや流れなどについては、あらかじめ葬儀社や喪主と打ち合わせをしておくと良いでしょう。
また、芳名帳自体は文具店や葬儀場などで購入可能ですが、通常は葬儀社が用意していることがほとんどです。
なお、芳名帳には個人情報が多数含まれるため、葬儀後も丁寧な取り扱いが求められます。
今後の法要(四十九日や一周忌など)で必要になる可能性もあるため、一定期間は保管しておくのが一般的です。
保管期間の目安は約10年程度とされ、処分する際は、情報漏洩を防ぐためにシュレッダーなどで処理することをおすすめします。
芳名帳の書き方とマナーを知ってスムーズな参列を
芳名帳は葬儀に参列した方の氏名や連絡先を記録し、返礼品や葬儀の案内を送る際に活用する帳面です。
参列者本人の名前と住所を省略せず、読みやすい字で正確に記載することが基本です。
ノート型では1人1行を使って縦書きで記載、カード型では1人1枚を使って記載します。
夫婦や家族で参列した場合は一人ひとりの名前を記載し、会社関係で参列した場合は故人様との関係性がわかりやすいように会社名や部署名も記載します。
受付として対応する際には、筆記用具を十分準備し、参列者への丁寧な対応を心がけましょう。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
芳名帳の準備や受付の進行についてもお気軽にご相談ください。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。