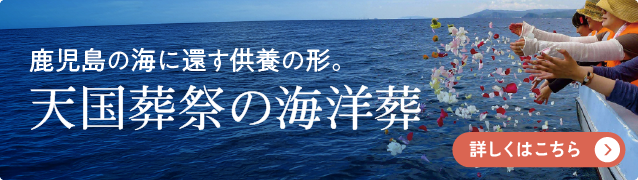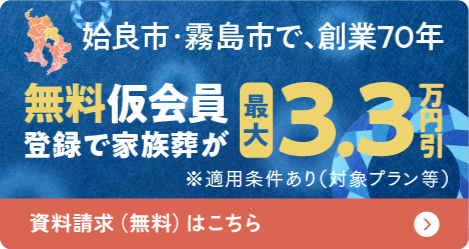こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の遠藤です。
お通夜や告別式に参列する際、誰もが一度は経験する「焼香」ですが、「正しいやり方がわからない」「宗派によって違いがあるのだろうか」と不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
焼香は、故人様への弔意を表す大切な儀式です。
今回は、焼香の基本的な作法や宗派ごとの違い、参列時に気をつけたいマナーについてわかりやすく解説します。

焼香の意味と基本的なやり方
焼香とは、葬儀や法事の際に香を焚いて故人様や仏様に敬意を表し、心身を清める仏教の作法です。
まずは、焼香の意味や基本的な作法について確認しましょう。
焼香の意味とは?
焼香には、大きく分けて次の3つの意味があります。
香りを供える
香(こう)は、故人様や仏様に香りを捧げることで、敬意や感謝の気持ちを表すものです。
仏教では、香りは故人様や仏様に届くとされ、心を込めたお供えとして大切にされています。
場と心を清める
焼香の香りや煙には、参列者の心身やその場の空間を清める意味があるとされています。
故人様を送り出し、仏様をお迎えする場を整える大切な役割を果たしています。
気持ちを整える
焼香の香りには、心を鎮め、穏やかな気持ちにしてくれる効果があるといわれています。
悲しみで落ち着かない心を整え、穏やかな気持ちで故人様に手を合わせるための助けとなります。
焼香の順番と形式
焼香は、故人様と関係が深い順に行われます。
一般的には、喪主→親族→一般参列者の順番です。
会場ではスタッフから案内されることも多いため、流れに従いましょう。
焼香には主に以下の3つの形式があります。
立礼焼香(りつれいしょうこう)
最も一般的な形式で、椅子席の会場などで立って行います。
以下のような流れで焼香を行います。
- 焼香台の手前で遺族と僧侶に一礼する
- 遺影に一礼する
- 右手で抹香(まっこう:焼香の際に使用されるお香)をつまみ、額のあたりまで持ち上げてから香炉にくべる
- 合掌し、再度一礼して席へ戻る
座礼焼香(ざれいしょうこう)
畳敷きの和室や自宅での葬儀などで用いられ、座ったまま焼香を行う形式です。
流れは立礼焼香とほぼ同じですが、動作は座った姿勢で行います。
- 中腰で焼香台へ向かい、座って遺族と僧侶に一礼する
- 遺影に一礼する
- 右手で抹香をつまみ、額のあたりまで持ち上げてから香炉にくべる
- 合掌し、再度一礼して席へ戻る
回し焼香
小規模な葬儀や自宅での法要などで用いられ、香炉が各席を順に回ってくる形式です。
席に座ったまま焼香します。
- 香炉が回ってきたら、前の方に軽く会釈して受け取る
- 自分の前に香炉を置き、遺影に向かって一礼する
- 右手で抹香をつまみ、額のあたりまで持ち上げてから香炉にくべる
- 合掌し、次の方に香炉を回す
宗派ごとの焼香の違いと注意点

焼香の作法や回数は、宗派によって異なる場合があります。
焼香のやり方に指定がある場合もありますが、基本的には自分の宗派の作法で焼香して問題ありません。
以下に、主な宗派ごとの焼香の回数と作法をまとめました。
なお、説明の中に出てくる「押しいただく」とは、抹香をつまんだ手を額のあたりまで持ち上げてから香炉にくべる所作で、敬意を表す意味があります。
【真言宗】
- 焼香回数:3回
- 作法:抹香を額に押しいただいてから香炉にくべる
- 補足:三宝(仏・法・僧)に敬意を示すための回数とされている
【浄土宗】
- 焼香回数:1〜3回(特に定めなし)
- 作法:抹香を額に押しいただいてから香炉にくべる
- 補足:合掌の際には「南無阿弥陀仏」を称える
【浄土真宗 本願寺派(西)】
- 焼香回数: 1回
- 作法: 抹香を香炉に直接くべる(額に押しいただかない)
- 補足: 合掌の心を重視し、形式よりも念仏の心を大切にするため押しいただかない
【浄土真宗 大谷派(東)】
- 焼香回数: 2回
- 作法: 抹香を香炉に直接くべる(額に押しいただかない)
- 補足: 本願寺派と同じく押しいただかないのが特徴。2回焼香する作法が伝統的
【日蓮宗】
- 焼香回数:1〜3回(特に定めなし)
- 作法:抹香を額に押しいただく
- 補足:合掌の際には「南無妙法蓮華経」を唱えることもある
【臨済宗】
- 焼香回数:1〜3回(特に定めなし)
- 作法:抹香を額に押しいただく
【曹洞宗】
- 焼香回数:2回
- 作法:1回目(主香)は押しいただき、2回目(従香)は押しいただかない
- 補足:煙が途切れないようにという配慮から2回行う
【天台宗】
- 焼香回数:1回または3回
- 作法:抹香を額に押しいただく
宗派がわからない場合は、一般的な作法で1回または3回焼香すれば問題ありません。
焼香の回数に迷う場合は、前の方の作法を参考にするのも一つの方法です。
大切なのは、形式よりも心を込めて焼香することです。
焼香のやり方にマナーはある?
焼香では、作法のほかにも気をつけたいマナーがあります。
これらのマナーを守ることで、より丁寧な焼香ができます。
数珠は忘れずに持参を
焼香の際に数珠は必須ではありませんが、持参が望ましいとされています。
数珠には略式数珠と宗派ごとの本式数珠があり、初めての方は略式数珠(1重のタイプ)で構いません。
なお、数珠の貸し借りはマナー違反です。
数珠は持ち主のお守りとされているため、たとえ親しい間柄でも貸し借りは避けましょう。
数珠がない場合の対処法はこちらをご覧ください。
手荷物は最小限に
焼香では両手で合掌するため、荷物は少なめにするのが基本です。
クロークがある場合は大きな荷物は預け、必要な物は小さなカバンにまとめておきましょう。
葬儀の際の持ち物に関してはこちらのコラムも参考にしてください。
焼香のやり方をしっかりおさえ、心静かにお別れを
焼香は仏教における大切な儀式であり、故人様や仏様への敬意を表す行為です。
宗派による違いがあるものの、基本的な所作や心構えを知っていれば、どの場面でも落ち着いて対応できます。
焼香の回数や押しいただくかどうかにとらわれすぎず、何よりも故人様を偲ぶ気持ちを大切にしましょう。
葬儀の場では、静かに、丁寧に、心を込めた行動を心がけてください。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。