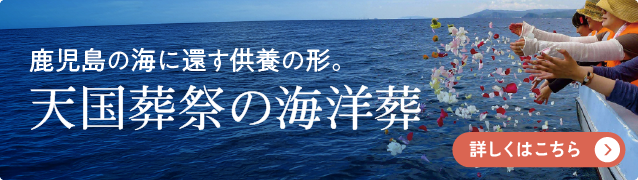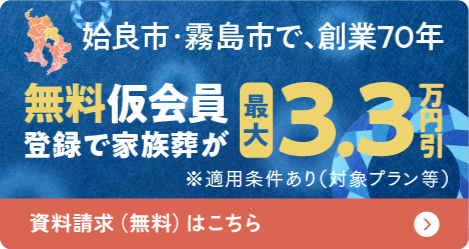こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の遠藤です。
葬儀に参列された際、会葬礼状と一緒に小さな袋に入った「お清め塩」を受け取ることがあります。
この「お清め塩」について、「いつ、どのように使えば良いのか」「本当に必要なのか」と戸惑われる方も多いでしょう。
そこで今回は、お清め塩の意味や正しい使い方、宗教による違いなど、知っておきたいマナーについて詳しく解説します。
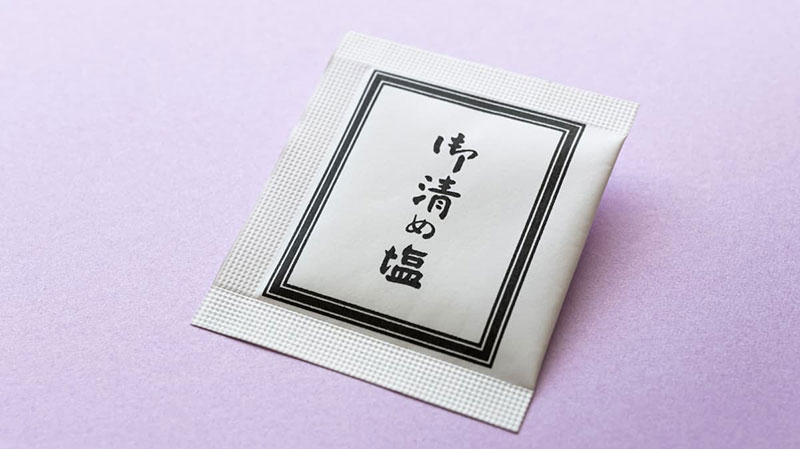
葬式のお清め塩の意味とは?
お清め塩とは、葬儀に参列した際に会葬礼状などと一緒に渡される、体を清めるための塩のことです。
葬儀から帰宅した際、自宅に入る前に体に振りかけることで、身についたとされる「穢れ(けがれ)」を祓うといわれています。
この習慣は、神道の思想を背景に、日本で古くから受け継がれてきました。
葬儀のあとに体を清める理由
神道では、死は「気が枯れる=穢れ」と考えられています。
この穢れは、生きている人にも伝染するとされ、葬儀に参列した人は一時的に穢れを受けた状態になるとされます。
そのため、自宅に戻る際はその穢れを家に持ち込まないよう、玄関の前で体を清める習慣が生まれました。
その清めの手段として、塩が用いられるようになったのです。
お清め塩の由来
葬儀のあと、体を清めるために塩が使われる背景には、神話的な理由と、生活に根ざした実用的な理由があります。
日本神話には、イザナギノミコトが黄泉の国から戻ったあと、海水で禊(みそぎ)を行い穢れを祓(はら)ったという記述があります。
この神話から、海水には穢れを祓う力があるとされ、やがて海水の結晶である塩が代用されるようになりました。
また、かつては火葬ではなく土葬が一般的であり、遺体の腐敗が疫病を引き起こす原因と考えられていました。
当時の人々は塩に殺菌作用があることを経験的に知っており、「塩で災いを退ける」という考えが生活の中に根付いていました。
こうした神話と生活の知恵が合わさり、塩によるお清めという風習が広まっていったのです。
葬式のお清め塩の正しい使い方と注意点

お清め塩には、正しい手順と注意すべきポイントがあります。
意味や手順を理解し、穢れを持ち込まないように正しく行いましょう。
お清め塩を使うタイミング
お清め塩は、葬儀から帰宅した際、玄関をまたぐ前に使います。
穢れを家の中に持ち込まないようにするのが目的のため、必ず家に入る前に行いましょう。
葬儀会場を出てから直接帰宅しない場合は、会場を出た直後に使っても問題ありません。
お清め塩の正しい使い方
お清め塩の基本的な使い方は、以下の通りです。
- 手を洗う(できれば参列しなかった家族に水をかけてもらう)
- お清め塩をひとつまみ取る
- 胸・背中・足元の順番で振りかける
- 服についた塩を手で軽く払う
- 地面に落ちた塩を踏んでから玄関に入る
塩は胸・背中・足元の順で振りかけ、最後に手で払い落とすのが作法です。
背中に塩をかけづらい場合は、肩の後ろ側(肩甲骨付近)にかけてもかまいません。
家族がいるときは、背中など手の届きにくい部分を手伝ってもらいましょう。
お清め塩を使う際の注意点
お清め塩を使う際は、いくつかの注意しておきたい点があります。
塩の量はひとつまみ程度で十分です。
大量に使う必要はありません。
体に塩をかけた後は、必ず手で払って塩を落とします。
塩が残ったまま家に入ると、かえって邪気を持ち込むとされています。
清めは必ず家の外で行い、玄関の中では行わないようにします。
最後に地面に落ちた塩を踏みしめてから玄関に入ると、邪気を断ち切るといわれています。
また、余ったお清め塩は、料理には使わないようにしましょう。
お清め塩は食用として作られておらず、乾燥剤などが含まれている場合もあります。
余った塩は普通ごみとして処分するか、気になる場合は、懐紙などに包んで捨てると良いでしょう。
葬式のお清め塩は必要?現代の考え方
現代では、お清め塩に対する考え方が多様化しており、必ずしも必要とされるものではなくなっています。
宗教・宗派による違いや、現代におけるお清め塩のとらえ方についてご紹介します。
宗教・宗派による違い
お清め塩は神道の思想に基づいた風習であり、すべての宗教で共通して行われるわけではありません。
特に仏教では、生と死を切り離さず一つの流れとしてとらえるため、「死は穢れたものではない」という考え方が一般的です。
そのため、仏式の葬儀ではお清め塩を用意しないケースも見られます。
中でも浄土真宗ではお清め塩を明確に否定しています。
「人は亡くなると同時に浄土に往生する(往生即成仏)」という教義に基づき、故人を穢れた存在と見なさないため、そもそも穢れを祓う必要がないとされているのです。
その他の仏教各宗派でも、「死を穢れとする考えは仏教本来の教義にはそぐわない」として、お清め塩を使わないところが増えています。
お清め塩が配られなかった場合は?
会葬礼状にお清め塩が入っていなかった場合、どうしても気になるようであれば、自宅にある食塩で同じ手順で身を清めることが可能です。
海水由来の塩(海塩)であれば、意味合いとしても問題はありません。
ただし、前述のように仏教では清める必要がないとされているため、特に気にならない場合は無理に行わなくても大丈夫です。
お清め塩に科学的・医学的な必然性があるわけではないため、迷信的と捉える人もいます。
一方で、心の整理や気持ちの切り替えの儀式として行う人も少なくありません。
あくまでご自身の気持ちや心情に応じて判断すると良いでしょう。
お清め塩の意味と正しい使い方をあらためて確認しよう
お清め塩は、神道の「死は穢れ」とする考え方に基づき、葬儀に参列した人が自宅に穢れを持ち込まないよう、玄関前で体を清めるために行われてきた風習です。
日本神話や生活の知恵から生まれたこの習慣は長く受け継がれてきましたが、仏教では「死は穢れではない」とされ、とくに浄土真宗ではお清め塩を使わない立場をとっています。
現代では、宗教的な立場だけでなく、個人の考え方や気持ちによって対応が分かれるようになってきました。
お清め塩を使うかどうか迷ったときは、その由来や意味、正しい使い方を知った上で、自分の信条や心情に沿って判断することが大切です。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。