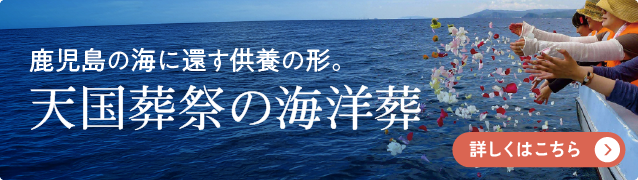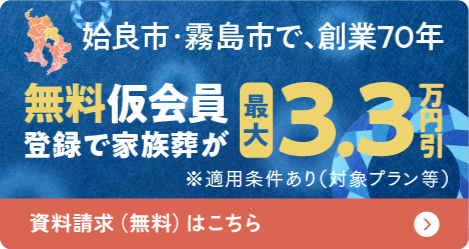こんにちは。 姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。
火葬後に行われる「骨上げ」について、マナーや作法がわからず不安に思われている方も多いのではないでしょうか。
骨上げ(こつあげ、ほねあげ)とは、火葬後に故人様のご遺骨を拾い、骨壺におさめる儀式のことです。
今回は、骨上げの意味や具体的なマナー、注意すべきポイントについて詳しくご紹介します。
初めて参列される方にもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

火葬後の「骨上げ」とはどんな儀式?
骨上げ(こつあげ、ほねあげ)とは、火葬後に故人様のご遺骨を箸で拾い、骨壺におさめる儀式のことです。
「収骨(しゅうこつ)」や「拾骨(しゅうこつ)」とも呼ばれています。
この儀式は日本特有の風習として受け継がれてきました。
海外では火葬の方法が異なることが多く、日本のようにご遺族が箸を使って丁寧にお骨を拾い上げる慣習は珍しいのです。
骨上げや骨上げ箸に込められた意味
骨上げには深い意味が込められています。
故人様をこの世からあの世に送る「橋渡し」をするという意味があり、そのため「箸」を使用するとされています。
骨上げに使用する箸は専用の特別なもので、普段使う箸よりも長いです。
また、木と竹など異なる材質で作られているものを一対として使うこともあります。
これは普段の食事では使わない「違い箸」と呼ばれるもので、日常とは異なる特別なときに使用することで、不幸が続くことを防ぐという意味があります。
地域による違い
骨上げの方法は地域によって違いがあります。
全国的に見ると、遺骨をすべて骨壺におさめる地域と、一部のお骨のみを骨壺におさめる地域があります。
また、骨壺の大きさも地域によって異なり、おさめる遺骨の量に応じて選ばれています。
骨上げのマナーについて確認

骨上げには決められた順番や作法があります。
事前にマナーを確認しておくことで、当日慌てることなく故人様をお見送りできます。
骨上げを行う参列者の順番とやり方
火葬が済むと、火葬場の職員が骨上げ台に遺骨を運び、参列者全員で遺骨を囲みます。
骨上げは故人様との関係が深い方から順番に行い、まず喪主から始まり、遺族、親族の順で進めるのが一般的です。
故人様と縁のある友人や知人の方も参加することがあります。
二人一組で行うことが多く、男女でペアを組む場合もありますが、同性同士でも問題ありません。
地域によっては、一人が拾った骨をもう一人に箸で渡す方法や、二人で一つの骨を同時に拾う方法などがあります。
火葬場のスタッフが案内してくれますので、指示に従って進めましょう。
骨上げを行う骨の順番
遺骨を拾う順番にも決まりがあります。
一般的には、足の骨から始まって上半身に向かって順番に骨壺におさめていきます。
足、腕、腰、背骨、肋骨、歯、頭蓋骨という順序で進め、最後に喉仏をおさめるのが基本的な流れです。
喉仏は仏様が座禅を組んでいる姿に似ていることから、骨壺の最後におさめるように大切に扱われます。
喪主と故人様に最も近しい方が一緒に拾うことが多いです。
喪主の役割ついては下記コラムでご紹介していますので、詳しくはこちらもご覧ください。
骨上げをする際の箸の使い方と作法
火葬後の骨上げには、火葬場で用意される専用の箸を使います。
箸の持ち方は普段と同じで構いません。
万が一、骨を落としてしまっても慌てずに再度拾い直しましょう。
骨上げの際に注意すること

骨上げを行う際には、いくつかの注意点があります。
事前に確認しておくことで、スムーズに儀式を進めることができます。
骨上げができない方に配慮する
骨上げは精神的に辛い儀式でもあります。
小さなお子様や体調がすぐれない方、精神的に辛い状況の方などは、無理に参加する必要はありません。
参列者全員が骨上げを行わなくても、故人様への供養の気持ちに変わりはありません。
それぞれの状況に応じて、できる範囲で参加しましょう。
分骨する際は事前の準備が必要
分骨が必要になるケースとしては、複数のお墓に納骨する場合や、手元供養を希望する場合などがあります。
その場合、分骨用の骨壺を事前に準備し、必要な手続きを行う必要があります。
分骨したお骨をお墓に納める場合は、分骨証明書が必要となります。
分骨証明書は、そのお骨が誰のものであるかを証明するための重要な書類で、火葬場で発行してもらうことができます。
なお、お墓に納骨せずに手元供養のみを行う場合には、分骨証明書は必要ありません。
分骨を希望する場合は、あらかじめ火葬場のスタッフに相談しておきましょう。
骨上げのマナーと意味を理解し心を込めたお見送りを
骨上げは故人様との最後のお別れとなる大切な儀式です。
骨上げには「故人様があの世への橋渡しをする」という深い意味が込められており、骨を拾う順番、箸の使い方など、細かな作法があります。
ただし、骨上げのやり方や作法は地域によって違いもあるため、火葬場のスタッフの指示に従って行うのが安心です。
骨上げに参加するのが難しい場合は、無理に参加しなくてもかまいません。
分骨を希望する場合は、事前に分骨希望であることを伝えておきましょう。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。